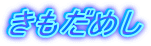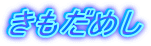参加者名簿(最終参加者数148名)
きもだめしの参加のためにウィズ便り(NO18)にて申込用紙を用意。それをもとに作成しました。 |
- 1・2年5人組、3・4年4人組、5・6年3人組を基本にして、任意でグループ分けをしました。
- 幼児は保護者同伴で、低学年のグループに入れました。
- グループ名は誰でも読めるひらがなにしました。
- 通し番号で総数がわかるようにしました。
- 受付欄、帰宅欄ともに、保護者と受付を通った人のみを記入。防犯上子供が一人で帰ることがないようにしました。
- 出発欄は、確実に出発したことを確認。
- くじ番号は確実にきもだめしから帰ってきたことを確認するために設けた「くじ」の番号を記入。
|
| 参加カード |
- 防犯上、受付を通るときは必ず保護者同伴であることを確認するため、子供と保護者とのペアを確認するカードを作りました。
- グループ名と通し番号が書かれていて、子供用はひもをつけ、首にかけられるように工夫しました。
|
各係の仕事説明
①お手伝いしてくださる父兄用
②ウィズメンバー用 |
- ① お手伝いしてくださる父兄を各係に任意で割りふったため、その方たちにあらかじめおおまかな係の内容を伝えておく必要がありました。(詳細は当日)
- ② 進行していくメンバー用には係の詳細を書きました。共通理解を深めるため、全員が各係の仕事内容を読むことにしました。
|
一般参加者への説明
(ウィズ便りNO20) |
- 来場時の車についてや、受付時の注意など、参加者全員に知っておいて欲しいことをまとめ、便りにて知らせることにしました。
|
| くじと、くじの景品 |
- 防犯上、きもだめしから確実に帰ってきた事の確認を取ることと、子供が確実に保護者と一緒に帰るようにするため、「くじ」による景品を渡すことにしました。
- メンバーが自宅のものを持ち寄りました。
- くじと景品は1対1で組ませました。(1番は1番の景品)
|
| ポスター(B4) |
- 当日、大騒ぎな学校の周辺に住む方々への理解をいただくため、学校の入り口4カ所に「きもだめしやってます」のポスターを貼りました。
|
| グループのプラカード(B4) |
- 当日、受付を済ませた子供達をグループ別に並ばせるために作りました。
- これがあったおかげで、マイクでの呼び出しをすることなく、スムーズに進行しました。
|
参加者への説明(模造紙)
①注意事項
②きもだめしのながれ |
- ① ウィズ便りNO20に書いた事項を中心に、守ってもらいたいことを書きました。
- ② 簡単なながれの説明を箇条書きにしました。
|
| 靴用のビニール袋 |
- 参加者の靴を各自で責任持って持ち歩くために、レジ袋を用意しておきました。
|
| 待ち時間用ビデオ |
|